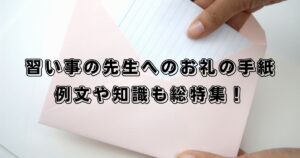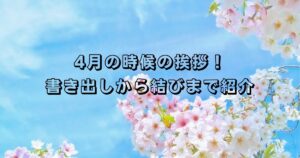✅11月に用いる『時候の挨拶』を基本的なことから解説してます
✅11月の時候の挨拶を書き出し~結びまで例文を取り入れてます
✅例文をそのまま手紙に使ってもらえます
11月になりますとスーパーやデパートでもボジョレーヌーボーのアナウンスが聞こえているのをご存じでしょうか❓ちなみにわたしは手紙を書くようになってから季節限定の言い回しが自然と耳にはいるようになりました!
ただ、目上の方や企業間で差し出す手紙に用いる『時候の挨拶』は漢文調でありますのが一般的ではあります。そのため、意味や用いる時期がわかりにくいことから苦労をした経験があります。
そうした経験をもとに11月に手紙を書く方が『11月に用いる時候の挨拶』を参考にできるようにとシェアさせて頂きました!是非とも参考になりましたら幸いです👌

『11月の時候の挨拶』と言われても不安になってしまうこともありますので基本的なことから振り返ってもらえると助かります❕
基本的な11月の時候の挨拶

それでは、『11月の時候の挨拶』についてみていきましょう👍
11月の挨拶を見ていく前に『時候の挨拶』を簡単に触れておきますね。
時候の挨拶とは:
:手紙の前文で頭語の後に記述する季節の挨拶となります。昔から手紙には様々なルールが存在します。そうしたルールは手紙の伝統や作法として見られておりますため、作法に則って手紙を書いた方が丁寧に見られます。もう少し平たくいいますと、本文を記述する前の手紙での挨拶となります。
日常生活で人とお会いした際にも、「こんにちは」「お久しぶりです。いかがお過ごしでしょうか?」「ご機嫌よう」などと挨拶をしますよね!
では、本題の『11月に用いる時候の挨拶』へと戻りましょう。
基本的な時候の挨拶ですが差し出すお相手により以下の3つの場合に分けております👍
◆固さが必要な場合
◆一般的な手紙の場合
◆フランクな手紙の場合
固さが必要な手紙の場合~漢語調~
こちらは、伝統ある手紙の作法を意識した形式!目上の方や会社として差し出す手紙はこちらの形式が多いです。
見た目は漢文調のため少々とっつきにくさがありますので、意味は下記を参考に確認してくださいね。前文に用いるために書き出しのワードとなりますよ。
| 例 | 読み方 | 意味 | 時期の目安 |
|---|---|---|---|
| 深秋の候 | しんしゅうのこう | (暦の秋は8月上旬~11上旬頃)秋が深まり終わりを感じるこの頃、 | 10月上旬~11月中旬 |
| 晩秋の候 | ばんしゅうのこう | (暦の秋は8月上旬~11上旬頃)秋も終わりのこの頃、 | 10月上旬~11月上旬 |
| 季秋の候 | きしゅうのこう | (暦の秋は8月上旬~11上旬頃)冬の終わりを感じるこの頃、 | 10月下旬~11月上旬 |
| 立冬の候 | りっとうのこう | (立冬は暦では11上旬~11月中旬)冬の始まりを感じるこの頃、 | 11月上旬~11月中旬 |
| 落葉の候 | らくようのこう | 落ち葉が舞う冬になってきたこの頃、 | 11月中旬~11月下旬 |
| 初霜の候 | はつしものこう | 今年最初の霜が降り始めるこの頃、 | 11月中旬~11月下旬 |
| 向寒の候 | こうかんのこう | 寒い季節にむかうこの頃、 | 11月中旬~12月中旬 |
| 霜寒の候 | そうかんのこう | 霜がおりるほど寒くなったこの頃、 | 11月下旬~12月初旬 |
| 氷雨の候 | ひさめのこう | 冷たい雨を感じるこの頃、 | 11月下旬~12月上旬 |
書き出しのワード一覧
~使い方~ 完成形:
:「深秋の候、晩秋の候、季秋の候、立冬の候、落葉の候、初霜の候、向寒の候、霜寒の候、氷雨の候、」
手紙をかく習慣がある方や目上の方にはこちらの形が必須です!それだけに使っていることに満足せずに時期があっているか確認をおこたらずにいきましょう🙇🏻

書き出しの言葉+の候(みぎり)
あとは11月に用いても大丈夫か確認すればオッケー❕
一般的な手紙の場合~和語調~
固さが必要な場合で紹介した言い回しを用いても問題ないですが、お相手によってはやや柔らかい言い回しにしても大丈夫でしょう。
| 例 | 時期の目安 |
|---|---|
| 北国から初雪の知らせが届く頃になりました。 | 上旬頃 |
| 暦の上では立冬となりましたこの頃、 | 上旬頃 |
| ゆく秋の感慨深い今日この頃、 | 上旬頃 |
| 菊の香り漂う霜月を迎えましたが | 中旬頃 |
| 晩秋とはいえ、うららかな日和が続いております。 | 中旬頃 |
| 冷気一段と強まり、いよいよ秋も深まって参りました。 | 中旬頃 |
| 初霜の知らせを耳にする今日この頃、 | 中旬頃 |
| 風に散る木の葉に深まりゆく秋を感じる時節、 | 中旬頃~ |
| ずいぶん日が短くなりました。 | 中旬頃~ |
| 木枯らしがわずかに残った紅葉を連れ去り、すっかり冬木立になりました。 | 下旬頃 |
| 霜枯れの季節を迎え、冬の訪れを感じます。 | 下旬頃 |
| ボジョレーヌーボーが楽しみな時期に参りました。 | 下旬頃 |
| 小雪を迎えても穏やかな気候が続いております。 | 下旬頃 |
| 冷気が一段と強まって参りましたこの頃、 | 下旬頃 |

手紙を出す目的にもよりますが、あまり親しい言葉になりすぎずお相手に合わせて表現したくはありますね!
フランクな手紙の場合~和語調~
さあ、ここからは普段の言葉遣いに近いものですのでイメージもしやすくなりますよ。
ぜひ皆様も11月になると目にする光景を想像しながら考えてみましょう!
●冬の気配が刻々と感じられる季節になってきましたね。
●近所の神社は、七五三の晴れ着に身を包んだ家族連れの笑顔でにぎわっておりました。
●初霜に驚かされました。
●日増しに暖かくなってまいりましたが、ご家族の皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。
11月を表す単語やイベント
11月を表す単語をうまく使うことで、自分ならではの表現ができます。フランクな手紙の場合にはなりますが、11月に贈る手紙に参考になりそうな事項をまとめてみましたのでぜひ!
| 例 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 立冬 | りっとう | 二十四節気のひとつです。暦の上で冬が始まる日を表す |
| 小雪 | しょうせつ | 二十四節気のひとつ。雨が雪にかわりはじめて冬に近づくことをあらわす |
| 菊日和 | きくびより | 菊の花盛りの時季に見られる秋晴れ |
| 小春日和 | こはるびより | 小春(旧暦の十月頃)にみられるあたたかな晴天 |
| 神楽月・子月・霜降月・建子月・帳月・天正月 | かぐらづき・ねづき・しもふりづき・けんしげつ・ちょうげつ・てんしょうげつ | 11月 |
| 七五三 | しちごさん | こどもの成長を祝う伝統行事 |
| ボジョレーヌーボー | ぼじょれぬーぼー | フランスのボジョレーで作られるワイン。毎年11月第三木曜日に解禁される |
| 木枯らし | こがらし | 木々を枯らしてしまうような冷たい風。別名「木の葉おとし」 |
~使い方~
完成形 ➡ 「寒気にも早春の息吹が感じられるようになりました。」

あ~!なるほど、、普段の会話に近しい言い回しだわ、、ここきて時候の挨拶が一気にイメージしやすくなったわね


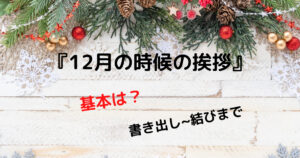
11月に使える時候の挨拶をシチュエーション別に
ここからは11月の季節の挨拶を取り入れた手紙の例を紹介していきますよ。 せっかくですのでこの時期に関連した例にしました。ほんの一例ではありますが参考にしてみてください。
ビジネスで送る手紙の場合
下記のは「開店祝いの御礼」の手紙の一例です。
ビジネスの場合はある程度きまった形を意識して書いた方がよいでしょう。
■開店祝いの御礼の場合■
さて、このたび開店に際し、お心尽くしのご祝詞とお祝いを頂戴しご厚情に御礼を申し上げます。
こうして何とか開店を迎えられましたのも、ひとえに皆様の温かいご支援とご指導の賜物と、深く感謝いたしております。
今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
敬具
令和〇年11月8日
株式会社 ダッツ 鈴木 太郎
株式会社 代表取締役 南 洋子 様
プライベート(かしこまった状況)で送る手紙の場合
「来年成人式を開催するご案内の手紙」の一例です。
上記の例と比べるとやや一般的な表現になっていますが案内状ということもありビジネスよりの例ではございます。成人式自体は1月にはなりますが事前のご案内例となりますのでご了承ください。
■ダッツ市成人式開催のご案内■
令和〇年11月11日
新成人各位殿
ダッツ区民館 会長 鈴木 太郎
令和〇年
成人式のご案内
過ぎ去る秋に哀愁を感じる深秋の候となりましたがいかがお過ごしでしょうか。
明春に成人式を迎えらますこと心より御祝い申し上げます。
さて、ダッツ町では来る1月11日(日)にダッツ町成人式の開催を予定しております。
つきましては是非、ご臨席下さるようにお願い申し上げます。
記
・日時:二〇三〇年1月11日(日)
受付8時~8時50分
・会場:「ロイヤルアリーナ」
・住所:東京都○〇区……
・内容 : オープニング、町長祝辞、来賓祝辞、
新成人の決意スピーチ、記念撮影等
*出欠のご返事を12月20日までに同封の返信はがきにてお願い申し上げます。
お問い合わせ先
区社会教育委員会
成人式担当 松村 Tel:**-****-****
プライベート(親しい相手)で送る手紙の場合
下記のケースは友人新築祝いの手紙の一例です。
相手との関係性や距離感はありますが!親しい相手へに手紙を送る場合は「折や折柄、この頃」「頭語(拝啓)、結語(敬具)」などはあまり意識しすぎずに表現して手紙を作成するほうがのぞましいでしょう!! このあたりは相手にあわせて柔軟に考えてよいとおもいます。
■友人のマイホーム新築祝いの場合■
ここしばらくは心地よい菊日和ですね。
この度は待望のマイホームを新築された由、誠におめでとうございます。
洋風な造りでデザインにも恵美子さんが関わられているとお聞きしました。お子様やご家族もとても喜んでいるのではないでしょうか。地価が高騰のこの頃ですが、設計までもこだわりの1戸建てのマイホーム。正直うらやましいです(笑)
近々、拝見に伺わせていただきたいとおもっております。恵美子さんにもよろしくお伝えくださいね。
ダッツ
結びに用いる『11月の時候の挨拶』
ここまでは、主に前文での書き出しで時候の挨拶を用いるケースをお渡ししていきましたが、実際には、手紙の締めの部分で用いることもできます。
そうした場合にはどのようになるのか合わせてみましょう👍
基本的には言い回しは似通ってきますが、挨拶でいいますと『さようなら』と去り際にお伝えする形式となります。そこだけは意識しながら形を見ると「うんうん」と納得しながら進みやすいはずであります。
こちらも書き出しの場合と同じく以下3つに分けております。
●固さが必要な手紙の場合
●一般的な手紙の場合
●フランクな手紙の場合
固さが必要な手紙の場合
例)
・天候不順の折、皆様のご健康お祈り申し上げます。
・寒さにむかう折柄、体調崩されませんようにご留意ください。
・夜寒の折、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
・向寒の時節、体調を崩されませんようにご自愛ください。
・本格的な寒さに向かいます折、皆様のご自愛お祈り申し上げます。
一般的な手紙の場合
例)
・秋晴れのすがすがしい日々、益々のご活躍をお祈りいたします。
・秋寒の季節ですので、くれぐれもお体おいといください。
・本格的な寒さに向かう時節、風邪など召されませぬようにおいといくださいませ。
・年末にむけてお忙しいとは存じますが、お元気でご活躍くださいませ。
フランクな手紙の場合
例)
・先日、早くも木枯らし一号が吹きました。急な冷え込みに体調を崩さないように。
・街は冬の装いです。温かくしてお過ごしください。
・めっきり寒くなりましたね。健康第一で頑張って。
・冬支度を早めに行い、お互いに風をひかないようにしましょう。
・温泉が恋しくなる季節になりましたね。ぜひご一緒できればとよいですね。
最後に
11月は季節感も冬に近づいてくることになります。この時期の時候(季節)の挨拶は、「落ち葉が散っているこの頃」など秋の哀愁漂う風景をそのまま表現してしまうと少しマイナスのイメージを与えてしまうこともありがちです!!
ですので「落ち葉舞う中でのウォーキングも味わい深い季節になりましたね」「散った落ち葉に日差しが当たると綺麗に見えるこの頃」などとできるだけポジティブな印象をあたえる表現にできるとよいでしょうね! あらためて11月の季節の挨拶を選ぶ大事な2つポイントをおさらいしておきましょう!
・差し出す相手との関係性
・相手に届く時期
この2つを意識すると時候の挨拶の言い回しを用いる際にどのような形式を選べばよいかのイメージがしやすいでしょう。可能ならの地域柄や天候も調べているとより気持ちが伝わった手紙を書くことができます。
是非とも、11月の時候の挨拶をうまく活用してくださいね😊