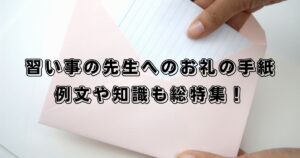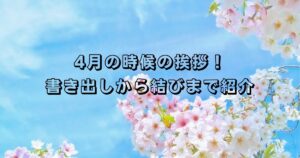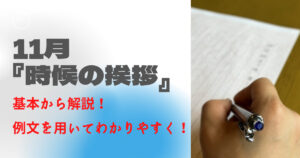6月に入りますと雨の気配がしてくる時期になりますね。今回はこの時期に手紙やはがきを書くにあたり用いることがあります「入梅の候」についてみていきましょう😊
「入梅の候」にかぎらず漢文調の季節の挨拶は意味がイメージしづらかったり、使う時期がわかりづらかったりしますよね。
仕事でも手紙やはがきに執筆に携わりますメッセージ部室長の私としましては関連する手紙部門における『時候の挨拶』のには素通りすることもできないわけでありまして。
この度、比較的じっくり消化することができたと感じましたのでこれから手紙を書く皆様のために意味や使う時期をわかりやすくまとめてたものをお渡しいたします👌
基本的な情報

入梅の候
読み方 :にゅうばいのこう
意味 :梅雨に入ったこの頃。梅雨の時期になった昨今。
※時候の挨拶でもちいる
「入梅の候」の言い回しは言葉のとおり、梅雨に入る時期のことをあらわします。6月の季節感としては梅雨の長い雨の期間は外すことができないです。旧暦のうえでは夏の期間中ではありますが、日本の季節感を表現するにあたり避けて通れない言い回しといえると思います。
いつからいつまで
では、「入梅の候」はいつころからいつまで用いることができるのでしょうか❓「入梅」の意味に注目していきながら、梅雨に入るとはどういうことかも詳しく掘り下げていきたいとおもいます。では、さっそくみていきましょう👍
入梅(梅雨に入る)とは
まず、「入梅」に関する辞書的な意味を確認しましょう。
梅雨の季節にはいること。太陽の黄経が八〇度に達した時をいい、暦の上では六月一〇日頃にあたる。
引用元:精選版 日本国語大辞典
難しいことばも並んでいますが入梅は梅雨の季節にはいることをあらわしているといえますね。では梅雨入りしたとはどういうことから判断していくのでしょうか❓
梅雨入り、梅雨明けを多くの方はニュースや天気予報で知ることがおおいとはおもいますが、梅雨入り梅雨明けは気象庁から発表されることになります。
基本的には今までの天候をもとに1週間以上先の天候と比較して雨などが多くなるころを梅雨入りと決められるようです。専門的な話としては梅雨前線が停滞することにより判断することがおおいようです。
直近の梅雨入り時期と結論
参考までに直近の梅雨入り時期(直近5年)を参考にみてください。
| 梅雨入り年 | 九州北部 | 近畿 | 関東甲信越 | 東北南部 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6/20頃 | 6/20頃 | 6/7頃 | 6/30頃 |
| 2018 | 6/5頃 | 6/5頃 | 6/6頃 | 6/10頃 |
| 2019 | 6/26頃 | 6/27頃 | 6/7頃 | 6/7頃 |
| 2020 | 6/11頃 | 6/10頃 | 6/11頃 | 6/11頃 |
| 2021 | 5/11頃 | 6/12頃 | 6/14頃 | 6/19頃 |
引用元:気象庁
直近の梅雨入り時期をみましたら6月上旬からが多い印象です。
これらを踏まえて一般的に用いる時期は
としております。
●宛先であるお相手の地域の梅雨入りをニュースや天気予報にて確認する。梅雨入りを確認してから使うのがよいでしょう。
●地域により梅雨の時期が異なります!北海道は梅雨がないので注意する。
例文~形式別~
こちらでは実際に「入梅」をもちいた言い回しを見ていきましょう。人によっては梅雨入りはポジティブでないとイメージする方も少なくないですので、季節の挨拶の後にはお相手の安否を問う挨拶を用いるか、できる限りポジティブな言い回しにするように心がけるとよいと思います。
改まった形式
●入梅の候、ご壮健のことと拝察いたします。
●入梅の候、貴社におきましてはご清祥のこととお慶び申し上げます。
一般的な形式
●入梅の折、紫陽花にしたたる雨が鮮やかになりました。
●入梅の季節柄、お変わりなくお過ごしでしょうか。
やわらかな形式
●いよいよ梅雨入りになりました。いかがお過ごしでしょうか。
●本日はまさに梅雨入りでした。例年のようにしばらく辛抱ですね。ご様子はいかがでしょうか。
最後に
さあ、いよいよ「入梅の候」についてもまとめに入っていきましょうか!用いる時期は記述したとおりですが、一般的には入梅の日を目安にする必要がある時候の挨拶といえそうですね。
それでは「入梅の候」をもちいる際のポイントをあらためて確認しましょう。
●お相手の方の季節のイメージを想像してみる
●実際の梅雨入りを天気予報やニュースで確認する
ぜひ「入梅の候」をもちいてよい手紙を贈ることができるようお祈り申し上げます😊
※6月に用いる時候の挨拶をあれこれ記事にしておりますので合わせてチェックしてくださいね