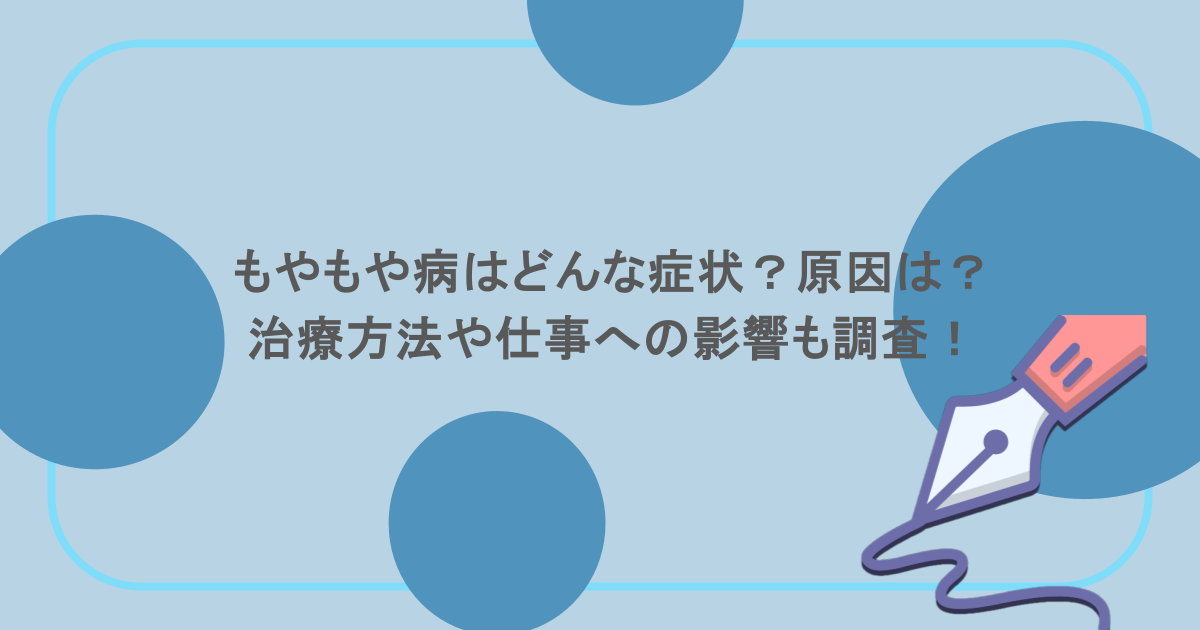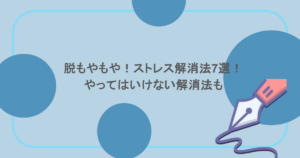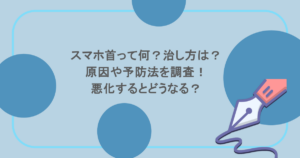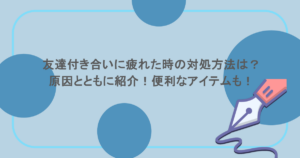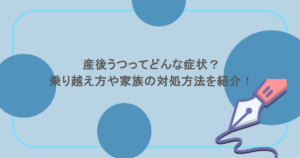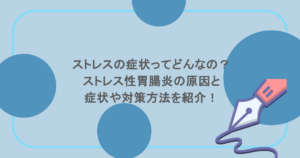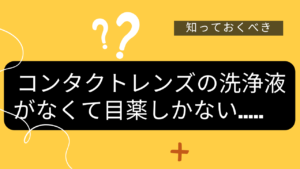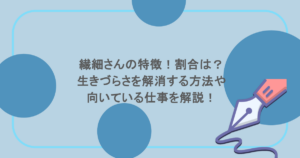脳に関する病気には、多種多様な種類がありますが、「もやもや病」はその名前の特異さから有名となっています。もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)は、脳底部の内頚動脈終末部などが進行性に狭くなり、代償として細かな側副血行(「もやもや」と見える血管網)が発達する希少疾患です。小児と若年〜中年の二峰性にみられ、虚血発作や脳出血で発覚することがあります。診断・治療は専門性が高い一方で、適切に設計された手術や生活設計で再発リスク低減と就学・就労の両立が目指せます。本文ではもやもや病はどんな症状なのか、原因仮説、診断、治療選択、手術後の経過、仕事への影響と配慮のポイントまで、要点を整理します。
もやもや病はどんな症状なのか?
「もやもや病はどんな症状が出るか?」という点については、小児かどうかによっても変わります。一般的な脳血流が足りない虚血型では、手足のしびれ・脱力、言葉が出にくい・ろれつが回らない、一過性黒内障などが反復されることが特徴点として挙げられます。小児では息を強く吐く・走るなど過換気で発作が誘発されやすいのが特徴です。成人は脳出血で発症することもあり、激しい頭痛や意識障害、麻痺が出ます。もやもや病の症状は一過性脳虚血発作(TIA)から脳梗塞・脳出血まで幅があり、これらの症状を自覚した際には早期の医療機関への受診が重要です。
原因と関連要因
もやもや病の本質的な病因は未解明ですが、発症する人が多い地域としては東アジアで頻度が高く、遺伝学研究からRNF213(p.R4810K など)が主要な感受性遺伝子と判明しています。なおこのリスク遺伝子を保因していることが必ず発症することに直結するわけではないことは留意しておく必要があります。「もやもや様血管病変」を伴う類もやもや病では、ダウン症、神経線維腫症1型、甲状腺疾患(バセドウ病/橋本病)がリスク因子として挙げられ、また頭蓋放射線治療後などの基礎疾患と関連が報告されています。甲状腺機能の変動が虚血イベントに影響し得る点にも注意が必要です。
一般的な診断方法と治療方法
初期はMRI/MRAで主幹動脈の狭窄と側副血行を評価し、必要に応じて脳血管造影で確定診断・手術適応を検討します。脳血流評価(ASL-MRI、SPECT、PET、アセタゾラミド負荷など)で「どこがどれだけ不足しているか」を見極め、方針決定に用います。成人では甲状腺機能や自己抗体、膠原病スクリーニングを追加することがあります。急性期(TIA/脳梗塞/出血)では血圧・脳圧管理などの内科的治療が主体です。再発予防と脳血流改善には外科的血行再建術(バイパス手術)が標準となり、虚血型や血流予備能低下例で検討します。抗血小板薬は虚血イベント抑制に処方されることがありますが、適応は個別判断です。
手術による治療方法
手術の代表は浅側頭動脈-中大脳動脈(STA–MCA)吻合などの直接バイパスで、術直後から血流が増えます。硬膜・筋・浅側頭動脈などを脳表に接触させ新生血管を促すEDAS/EMS等の間接法、両者の併用も行われます。小児では間接法、成人虚血型では直接、併用を選ぶ傾向があります。合併症予防のため周術期は過灌流や梗塞を厳重に監視します。多数の観察研究では、手術による血行再建により虚血発作の再発減少、脳血流・症状の改善が示唆されています。併用術(STA–MCA+EDAS)で血行動態や機能転帰が改善した報告もあります。
再発防止と生活のコツ
もやもや病では過換気や強い息こらえ、脱水、急激な高温入浴などの状態は血流の揺らぎを招くため回避するようにしましょう。また発熱や甲状腺機能亢進など全身状態の変動時はもやもや病の発作が増えることがあり、基礎疾患のコントロールが重要なポイントになります。水分・睡眠・ストレス管理、寒暖差対策、感染予防、規則的な軽運動やリハビリで体力・バランスを底上げしましょう。基本的には、もやもや病はどんな症状が出るのかという点や、関連要因に応じて生活スタイルを調整することが求められます。
仕事や学校への影響、生活への影響
症状のない時期でも、脳疲労感、注意・処理速度の低下、頭痛が残ることがあります。発作誘発要因(長時間の過換気を伴う肉体作業、熱環境、極端な残業)は調整し、こまめな水分補給・休憩、寒暖差対策、在宅や時差勤務などを産業医・学校と相談します。術後の短期は過度な気圧・温度変化や長距離移動を避け、段階的に復帰。運転可否や高所作業は主治医判断に従いましょう。小児は過換気誘発のTIAが目立ち、発達・学習面のサポートを含む長期フォローが推奨されます。妊娠・分娩は循環動態が大きく変化するため、周産期チームと事前に分娩計画を作成します。
受診するべき症状の目安
もやもや病の受診の目安は明確です。「片側の手足が急に動かない」、「言葉が出ない・ろれつが回らない」、「激しい頭痛」、「視野が欠ける」は救急要請のサインとして押さえておく必要があります。また小児で“ふーふー”と吹く・楽器演奏・全力疾走の直後に一過性の脱力や無言が出る場合も受診をすることが求められます。既往者で新たな神経症状が出たら速やかに主治医へ連絡しましょう。相談先は脳卒中・脳血管外科の経験豊富な専門施設が推奨で、国立循環器病研究センター等の専門外来なら診断〜手術〜周術期〜長期フォローまで一貫対応が可能です。地域の紹介体制、術式の選択肢、症例数や合併症率も確認すると安心です。
まとめ
もやもや病は、脳主幹動脈の進行性狭窄により側副血行が発達し、虚血発作や脳出血を来す希少疾患です。もやもや病はどんな症状が出るかについては、小児は過換気でTIAが誘発されやすく、成人は出血を伴う発症も発生します。診断はMRIとMRAと血管造影、血流評価で総合判断し、再発予防の主軸は血行再建術(直接・間接・併用)と全身管理です。生活では脱水・強い息こらえ・急な高温入浴を回避し、睡眠・水分・ストレス管理を徹底しましょう。就学・就労は在宅や時差勤務など環境調整で両立可能です。「片麻痺・失語・激痛頭痛・視野欠損」は救急サインです。専門性の高い脳血管外科で、術式・症例数・合併症率まで確認しつつ早期に相談しましょう。