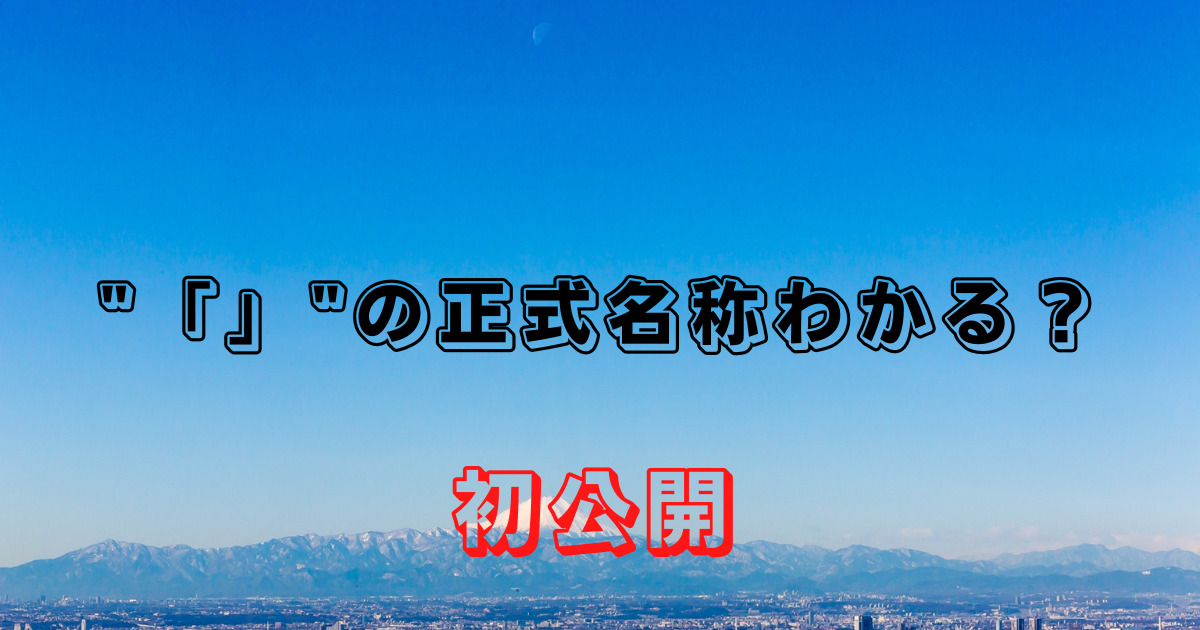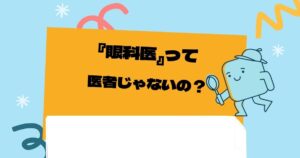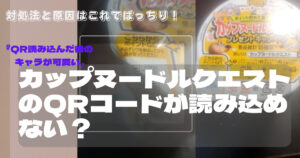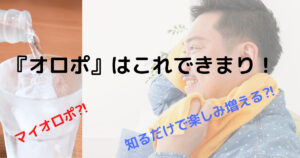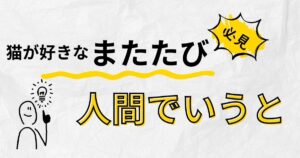どうも、夏真っ盛りということで「夏」と強調したくなるこの頃です。
冒頭の一行で用いていた”「」”ですが、頻繁に使うことがあっても意外と知らないよねと感じたんですよね。ということで、”「」”の初めの一歩である正式名称を調べてみました。
ということで、シェアさせて頂ければと思います。
正式名称から由来、使い方まで総特集しておりますのでぜひとも参考にしていただければと思っております😊
“「」”の正式名称は?
それでは結論といきましょう。
正式名称と断定することは難しいですが
鉤括弧(かぎかっこ)
と表現するのがよいでしょう
正式名称と呼べない見解とは
では、正式名称と呼べない個人的な見解を簡単にお伝えしていきましょう。
結論
根拠としましては、正式名称が正しいのか判断できないことがあげられます。
まずは正しい正式名称か判断できない件についてですが、”「」”の正式名称が仮に鉤括弧(かぎかっこ)だとします。ですが、命名者が不明なので、どこかの団体や機関が正式名称を公表しない限りは判断できかねます。
個人的な見解
個人的には、正式名称が必要ないという見方ができるのではと考えております。
先に正式名称が必要なケースをお伝えします。
たとえば、ここ数年流行しております新型コロナウイルスですが、世界保健機関がCOVID-19と名付けております。世界的な流行でありますので、正式名称が発表されていないとあちこちから色んな名前で呼ばれる可能性があります。
そうすると、いろんな名前で呼ばれることになりますので、新型コロナウイルスのことかどうかわからなくなりかねます。
医学的な論文や公的な文章に用いられることが多いため正式名称が必要となります。
一方で、”「」”の場合には、”「」”数多くある記号の中で日本独自のものです。つまり、世界共通のものでもありませんので、正式名称が必要ないケースとなります。
“「」”の文字を研究している研究者はいるかもしれませんが、正式名称として判断ができない状況ではないでしょうか。
※今後、文献等を含めて何か判明しましたら、情報を更新させていただきます予定となります。
由来
気になる方もいらっしゃるかと思いますが、詳細は定かではないです。ただし、有力な説としては、海外で用いられていた”()”に影響を受けたこと、および、庵点と鈎で鍵のように囲むことが由来とされております。
もう少しわかりやすく解説していきましょう。
庵点とは和歌や俳句などのはじめに置かれる記号の一つになりますが、改行を表す鈎画と庵点が囲むようであったことから、会話を囲む際に用いられるようになったと言われております。
使い方
一般的に”「」”の記号は主に文章で用いられる引用符や符号とされております。
では具体的な使い方をご紹介しましょう。
代表的な使い方3つにまとめております!
見て頂くとわかるとおもいますので参考にしてみてください。
①話した言葉や書いた言葉を文章中で表現するとき
“「」”に中に表現したい会話を入れることで話した言葉や文章を表現できます。
②文章のなかで人の思いや筆者の思いを表現するとき
小説や作文、エッセイなどで登場人物の思いを”「」”内に入れることで表現することができます。
③文中で他の言葉と区別するとき
固有名詞や作品名、または、章題を”「」”の中に入れることで表現することができます。
鉤括弧と表現するものは、”「」”だけでなく”『』”や”〔〕”などもあります。
”「」”を分解して ”「” は始め鉤括弧と表現されたり、”」” は終わり鉤括弧と表現されることもあります。
他の言い方
“「」”の鉤括弧(かぎかっこ)以外の言い方をお渡ししていきましょう。
●一重かぎ(いちじゅうかぎ)
●ひとえかぎ
●引用括弧
●括弧
●ひっかけ
最後に
“「」”の正式名称は鉤括弧(かぎかっこ)であるとは断定しずらい結論となりましたが、そうしたことも踏まえて捉えていただければと思います👌
正式名称の成り立ちは諸説ありますが、記号の1つの成り立ちも奥が深いんだなと感じながら、使い方もしっかり確認していきたいと思いました。
何気なく使っている記号も面白いなと思いながらこれから”「」”を使うとき親しみを感じるのではと思います。