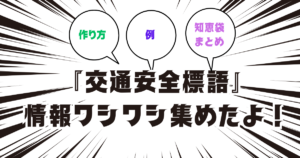運転することが多い私は、交通安全標語(スローガン)を読んで、運転中に意識していなかった気づきを得たことがあります🙇🏻
標語に限らず、あらゆるメッセージは作者の想いや思想を表現したもの。似たメッセージでも伝え方は人それぞれであります。
ですが、ついつい他の方の作品に影響を受けてスローガンを作ってしまったことはありませんか?
そうしたときに気をつけたいのがパクリです。今回は、交通安全標語(スローガン)を作るうえで知っておきたい『パクリ』についてクローズアップしていきますね👍
「交通安全標語(スローガン)」のパクリっていいの?
パクってもいいのでは!と感じる方もいるかと思いますが、、
といいますのも、、著作権という法律でパクるのが禁止されているからです。
著作権の目的は、作品を作った方の人格を守るという考え!と、作った方が所有する利益(経済的な)守る考え!によります。
では、他の交通安全スローガンをパクったのでは!と思われてしまう場合ですが、、次の章で触れていきましょう。
パクリと思われてしまうケースとは!
ではどのようなときにパクリと思われるのでしょうか?
まずパクリと思われてしまう代表的なケースですが、コピペして語尾や表記を変えただけ💦
例)
byメッセージ研究室
こういった交通安全標語があったとします、、
パクリになってしまうケース)➡NG🙅🏻♀️
『運転マナーまもってよ 遅刻しちゃう 関係ないぞ』byメッセージ研究室
誰がみても文章が非常に似ているケースは間違いなくパクリです。モラルや人として認められる行為ではないのは当然ですが、、訴えられる可能性もありますので、リスクも考えてコピペはやめましょう😢
また、完全にコピーしていなくても
と言い回しを一語変えた程度では、あきらかにパクってるよね💦
と思われます。コピペをベースにして調整を加えるような作品は避けましょう。訴訟になった場合には裁判官が判断することにはなりますが、、
パクるのではなく、型を参考にするようにしましょう。他の「交通安全標語」を手本として型を参考にする方法は次の章でお伝えしていきますね👍
他の「交通安全標語」を参考にする方法
さて、他の「交通安全標語」をパクるのはダメだと感じて頂けたとおもいます。ですが、一方で「じゃあ、どうしたらいいのですか?」といった声も聞こえてきました。
そこで、「パクリになってしまうのでは」と少しでも不安を感じている方にむけて【他の「交通安全標語」を参考にする方法】についてもお伝えしていきますね。
✔気になる表現の型をチェックする
✔専門用語をストックする
気になる表現方法の型チェックする
過去のコンクールの作品を参考にする簡単な方法は、【気になった作品の型や言い回しをチェックすること】です。
リズムや語順
「パクリがだめなのにどういった点を参考にするの?」
こう思われた方は、過去の入賞作品の型を参考にしてみてください。
「型」とは、色んな要素があるのですが、基本的なことで言えば「5・7・5」の形そのものや音のリズム感や語順、そして、スローガンのメッセージがどのように伝えられているのか!
言い回し
こちらのスローガンをご覧ください!
運転は ゆとりとマナーの 二刀流
引用元:令和5年使用交通安全年間スローガン 入賞作品 より
運転者(や同乗者)に訴えかける部門で内閣府特命担当大臣賞に選ばれた作品となります。
運転はゆとりとマナーが欠かせない!そうしたメッセージを二刀流という言い回しで表現しています。
二刀流と言えば、最近では「投手と打者」で活躍が話題の大谷選手!年代問わず多くの人が自然と興味を持ってしまうワードであります。
「それなら、私も使ってみよう~」と思うのではなく、二刀流のように世間で話題になっている言葉はないかな~!との発想で言葉を探すようにしましょう。
例えば、、(執筆時点2023/8/20)では自転車のヘルメットは2023/4/1からつけるようにしましょうと道路交通法が改正されて話題になっていますね。
そうした話題からスローガンを考えてもよいでしょう。
『着用しよう! ヘルメットで 助かる命』by メッセージ研究室
専門用語をストックする
そもそも自分が伝えたいメッセージを的確に表現するには、運転や車、交通マナーでしか使わないであろう【ワード】を知っていることが重要になります。
「ブレーキ」「アクセル」「点灯」「ガス欠」「イエローライン」etc
こうした知識が交通安全標語(スローガン)を作るうえで幅を広げることにつながりますよ~👌
可能なら交通安全標語の用語辞典みたいなものが作れると理想ですね。免許を取得した人なら知っているべき知識になりますが、人間は覚えた知識も忘れてしまいます。
スマホやPCで持ち運びできるのが理想です。

最後に
交通安全標語(スローガン)は、1つ1つ様々なメッセージですよね~🤔
もちろん、交通安全が大きなテーマ。とはいうものの、1人1人のストーリーが詰まっているメッセージです。
そう考えますと、コピペしなくても、感じたことを言葉にすることを考えてほしいと思いましたよ。