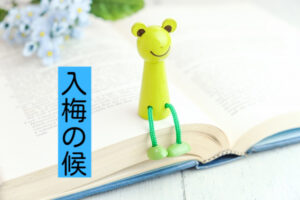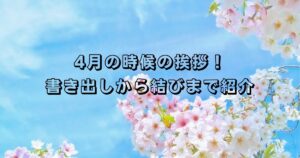梅雨も明けようかという時期になりますと今年も暑い時期に突入するのかしらと思いますね。今回はそのような夏を迎える時期に手紙やはがきの季節の挨拶に用いることがあります「向暑の候」についてみていきましょう😊
「向暑の候」のような普段の言葉では用いない形式の時候の挨拶は普段から手紙を書く方でも精通してなければイメージが難しかったりすることがありまして。
メッセージ研究室を通じて手紙やはがきに接している室長の私としては、管轄の手紙部門における時候の挨拶の領域にはどうしても素通りすることもできないわけであります。
時候の挨拶を用いる皆様が「向暑の候」を選ぶにあたり、時期や豆知識をなるべくイメージしやすいようにまとめていきますので参考にしていただけますと幸いです👍
基本的な情報

向暑の候
読み方 :こうしょのこう
意味 :(夏の)暑さにむかっている頃
※時候の挨拶でもちいられる
いつからいつまで
結論をいいますと
となります。
二十四節気の視点から
根拠の1つとしまして、二十四節気の時期を参考にしつつ結論を紹介していきます。まず、いつ迄ですが、梅雨明け後の暑さが始まる小暑としております。といいますのも、二十四節気の1つである小暑(7月7日頃~7月22日頃)は夏の本格的な暑さのはじまりをあらわすからです。
「~の候」と時候の挨拶で用いられる夏は二十四節気を基準としておりますので、気象庁や学校で言及される夏の時期と少しずれます。これは、二十四節気は太陽の動きを基準に24つの時期へと分けられてたり、中国の黄河流域の気候をもとにしているなどに起因します。
二十四節気があらわす夏の時期は下記のイメージを参考にしてみてください。わたしたちが現在使っている月日におきかえるといつごろをあらわしているのか一目でわかる表となります。ちなみに立夏(5月6日頃~)というのが夏の始まりです。

二十四節気の立夏とは
つぎに「向暑の候」をもちいるのは、いつから❓を二十四節気の立夏に関する意外な意味からちょっと考察してみましょう!
では、暑い時節へむかうのはいつからですか?私の所属するメッセージ部でも飛び交う質問ではありますが。実は二十四節気の「立夏」には前の季節である春が盛りを迎えていることを強調して、暑い夏へむかってますます暑くなるというニュアンスもあるようです。
立夏の終わりころからは暑い夏へ向かっていく節目といえるようです。つまり5月中旬頃~がいつからのはじまりになります。
向暑をむかえるうえで
「向暑」をもちいる時期は長いですが、本格的な暑さを迎えるうえで欠かせないことばについてみていきましょう。ぜひイメージしながらみると面白いかもしれません。
◆衣替え◆
6月を境に多くの地域で冬服から夏服へと衣替えが行われます。衣替えの起源は宮中行事の更衣ともいわれております。夏を迎える前に日常生活で積もった穢れを祓う目的もあったそうです。
◆夏越の大祓◆
本格的な暑い夏をむかえるにあたり、1月~6月の間に受けた邪気を追い祓う神事です。具体的には茅(かや)というイネ科の植物をもちいます。生命力が強いことから穢れを祓うのに適しているとされます。茅の輪を潜ることで半年の邪気を取り除くのが夏越の大祓になります。

例文~書き出し~
さて、向暑をもちいた手紙の書き出しをみていきましょう。書き出しについての構成は下記のようで大丈夫でしょう。
書き出しの構成について
・頭語➡・時候の挨拶➡・安否の挨拶or・感謝の挨拶or・慶賀の挨拶・ご無沙汰のお詫び
頭語が「拝啓」の場合は結びに「敬具」がセットになります。
※見やすさの関係で横書きのたとえを表しておりますが、「~の候」を用いるような改まった形式では縦書きが中心です。予めご了承ください。
改まった形式
●拝啓 向暑の候、貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
●拝啓 向暑の候、ますますご清祥のことと拝察いたし、なによりに存じます。
一般的な形式
●拝啓 向暑の候、ご健勝のことと存じます。
●拝啓 向暑の候、爽やかな風に濃い緑の葉が揺れております。皆様にはご壮健のことと拝察いたします。
やわらかな形式
●向暑の折、衣替えの季節となりましたね。いかがお過ごしでしょうか。
●日増しに熱くなってきました向暑の昨今、ご様子はいかがでしょうか。
最後に
さあ、いよいよ「向暑の候」についてもまとめに入っていきましょうか!用いる時期は記述したとおりですが、用いる時期だから使うのではなく他の時候の挨拶を含めて選ぶ必要があるといえそうですね。
それでは「向暑の候」をもちいる際のポイントをあらためて確認しましょう。
●二十四節気の夏の期間や暑さをあらわす小暑
●初夏や梅雨の時期など他の時候の挨拶を用いたほうがよい場合も考慮
ぜひ「向暑の候」をもちいてよい手紙を贈ることができるようお祈り申し上げます😊
※6月に用いる時候の挨拶をあれこれ記事にしておりますので合わせてチェックしてくださいね