9月も半ばになりますと朝夕はひんやりしてきましたでしょうか。今回はこの時期に手紙やはがきを書くにあたり用いることがあります「仲秋の候」についてみていきましょう😊
「仲秋の候」にかぎらずのような漢文調の季節の挨拶は意味がイメージしづらかったり、使う時期がわかりづらかったりしますよね。仕事でも手紙やはがきを書いておりますメッセージ部室長(自称)の私自身としまして管轄の手紙部門における時候の挨拶の領域には素通りすることもできないわけでありまして(笑)
これから手紙を書く皆様ができるだけわかりやすく意味や使う時期をイメージしやすくできるようにまとめていきますので参考にしていただけますと幸いです👍
秋にもちいる季節の挨拶は似たものが多くて困るのじゃ
基本的な情報

仲秋の候
読み方 :ちゅうしゅうのこう
意味 :(旧暦での)秋の真ん中のこの頃
基本的には時候の挨拶でもちいられる言い回しとなります。「仲秋の候」は「仲秋」と「候」のことばから構成されておりますが、「候」とは簡単にいえば「~の頃、~の季節、」という意味合いです。
では「仲秋」という単語については辞書的な意味合いから少し掘り下げてみていきましょうか。
旧暦の8月のこと。現行歴では白露(はくろ)(9月8日ごろ)から寒露の前日(10月7日頃)までにあたる。秋分を含む月が旧暦では8月と定義されている。
引用元:日本大百科全書
いつからいつまで
辞書的な意味から、仲秋は旧暦の8月にあたり二十四節気の白露と秋分にあたる期間ということが分かりましたね。二十四節気は聞いたことがあってもあまり見慣れないものですので、図でみていきましょう。
下記の図をみていだたけるとおわかりですが、秋を3等分した真ん中の期間をあらわしていますね。

よって用いる時期は
となります。
仲秋に関連することば
うえの章では意味についてを掘り下げながら使う時期についても見てきましたが、ここでは仲秋にまつわる言葉や季節感を紹介していきます。仲秋のイメージをする際にも参考にしていただければ幸いです。
仲秋と中秋
よく似ているために意味を間違えやすいことばとして「仲秋」と「中秋」があります。
仲秋は旧暦の秋の期間を三等分した真ん中の期間を表します。一方、中秋は読み方もおなじくちゅうしゅうでありますが、中秋は旧暦の8月15日、満月をさしますので要注意です。
仲秋の季節感
◆中秋の月◆
中国から伝わったことから始まった十五夜の月見の祭事。現代では月が見える場所で月見団子や里芋などを盛り月を眺める。
◆川内大綱引き◆
鹿児島県薩摩川内市で3000人の男衆が大綱を引き合う伝統行事。
例文~形式別~
ここでは仲秋をもちいた例文をみていきましょう。形式別にわけてありますので是非とも参考までに!
改まった形式
●仲秋の候、皆様にはますますご清祥のことと、心よりお慶び申し上げます。
●仲秋の候、ますますご清祥のことと拝察いたし、なによりに存じます。
一般的な形式
●心落ち着く仲秋の時節、ご健勝でございましょうか。
●実り多き仲秋の折、お変わりなくお暮しのことと存じます。
やわらかな形式
●今年は見事な名月が楽しめそうな天気予報になりますが、お変わりなくいらっしゃいますか。
●中秋の名月に秋の深まりを感じるこの頃、お元気にお過ごしでしょうか。
最後に
さあ、ここまで「仲秋の候」についてみてきましたがいかがでしょうか。用いる時期は記述したとおりですが、白露から寒露の前日まででしたら比較的にもちいやすい時候の挨拶といえそうですね。あとは二十四節気の秋の中頃が現行の月でいつをさしているか確認できるようにしましょう。
それでは仲秋の候をもちいる際のポイントをあらためて確認しましょう。
●お相手の方の季節感のイメージを想像してみる
●実際の季節感を天気予報やニュース、イベントで確認する
ぜひ「仲秋の候」をもちいてよい手紙を贈ることができるようお祈り申し上げます😊
※9月に用いる時候の挨拶をあれこれ記事にしておりますので合わせてチェックしてくださいね







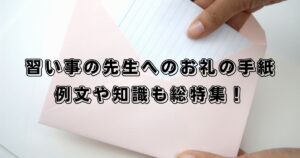
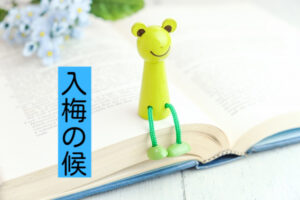
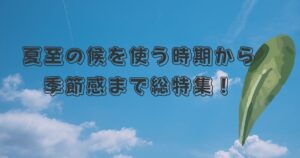

時期は目安です。手紙を贈るお相手の方が感じるであろう季節感を大切にしてみてください。