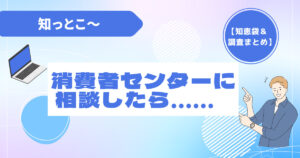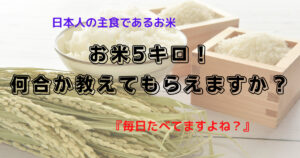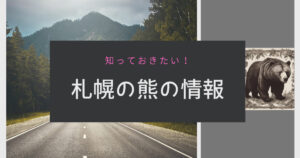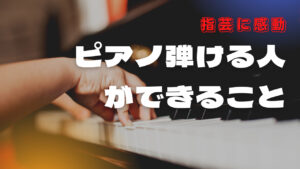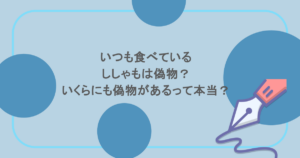小学生1~6年クラブコーチをしている友人が数か月に一回は「コーチのところに教科書の置忘れがありませんでしたか(泣)?」と生徒や保護者から連絡がくるんだよねと話題を振ってきたときがありました。
友人のコーチは独身でしたが連絡を受ける度に何かよい答え方はないかと困っているようでした。
子供たち教え子が教科書をなくしたときに何か気の利いたアドバイスを伝えて解決策を提示できるようにしっかり把握しておきたいとのことでした。
そのようなこともあり、忙しい友人の代わりに情報収集が比較的得意な私がリサーチしつくしてみました。友人にも伝えましたが、備忘録としてここにも残させていただきますね。
今回は、学生の息子さんや娘さんが教科書をなくしてしまったときの解決策、購入する際に押さえておきたいポイント、なくさないような生活習慣、なくしやすい場所と探し方、なくさないような対策のまとめ、について特集してみました。
教科書をなくした方にも参考にして頂きたい記事となっております👍
教科書をなくしたときの解決策
ここでは教科書が見つからないときの5つの解決法についてご紹介いたしましょう👍
先生に相談して購入
こちらは先生へ教科書をなくしましたと相談する方法となります。
正直なところ、学校の成績を気にしている方ですと少しでも先生へ心証がよくない行動はしたくないかもしれないですね。
そうした点も踏まえますと、ここでのポイントは「正直に理由を話すこと・ご迷惑おかけして申し訳ございません」としっかりと伝えて、今後の対策もしっかりと話すことができたらよいでしょう。
先生も人ですので、日頃の行いやミスした後の行動や言動を評価してくれるでしょう。
もし、クラブ活動などで仲のよい先生がいれば先にそちらに相談するのも1つの方法となります。
取り寄せて購入
先生に教科書を取り寄せて頂くのは避けたいときには、自分で取り寄せることになります。
個人的にはこちらの方法がお勧めとなります。
具体的には、「教科書・一般書籍供給会社」からお住いの地域の都道府県を選んでみてください。
そうすると、取り扱いしている書店が掲載されております。
教科書を大量に発注するわけではありませんので、1部でしたら書店の在庫に置いてある可能性が非常に高いです。
ですが、基本的には発注制をとっておりますので在庫がないケースは取り寄せに時間がかかると思っておいた方がよさそうです。
先輩に譲ってもらう
では、先輩に譲ってもらう方法を進めていきましょう。
この方法は、1学年うえの先輩に教科書を譲ってもらう方法となります。
必ずしも解決できるかどうかはわからないです。といいますのは教科書の内容が同じかどうかは確認しないと判断できないからです。
年度によって教科書のデザインや文章が違う場合には注意が必要となります。
小学生の図工の教科書などは、2学年用(1、2年生用・3、4年生用・5、6年生用)が多かったりしますので譲り受けても使い回すことができるかもしれないです。
ネットで探す
ネットで探して購入する解決方法となります。
探している書籍の名前、販売会社を友人に確認して、ネット上で販売している方がいないか探す方法となります。
ヤフオクやメルカリなどで出回っているかもしれないです。転校した方で教科書が必要なくなった方が処分するために出品していることも考えられます。
タイミングの問題もありますが、一度調べてみるのもよいでしょう。ただ、仮に購入できても到着までにはお相手の発送方法により早くても数日はかかりそうです。
友人のものを貸してもらう
では、最後にご紹介するのは違うクラスの友人に教科書を貸してもらう方法となります。
年度の初めに、なくした場合には1年間借りるのはどうかと思いますが、教科書を取り寄せている期間や次の学年まで残り1か月でしたら、別のクラスの友人に借りてもよいかと思います。
通常、クラスが違うと授業時間が違いますので、同じ時間に国語の教科書を使うことはないです。
教科書を購入する際のポイント
ここからは、購入する際のポイントをお伝えしましょう!
押さえておきたいポイントは、「価格」・「支払方法」・「到着までの期間」があげられます。
まず価格となります。小学生・中学生ですと1冊目は無償で提供されるかとおもいます。
ですが、再び購入する場合は2冊目となりますのでお金を出して購入することとなります。
年齢が上がるほど教科書の価格が高くなる傾向があります。小学生よりも中学生、中学生よりも高校生で使う教科書の方が扱う範囲が広くなり部厚くなるから仕方がありません。
小学生・中学生の教科書ですと高くても1冊でしたら1,000円前後で購入することができるでしょう。
ただ、お子さんが特別養護学校へ通われているケースですと、国語の教科書1冊は5,000円~1万円まで幅を見ておいた方がよいでしょう。
次に、支払方法です。
基本的に、購入するケースは現金払いが基本となります。
学校での教科書販売日にクレジットカードで購入しているクラスメイト、先輩や後輩を見た人はいないのではないでしょうか?
これは、教科書の販売には国家予算が関係しており、販売会社がクレジットカードの手数料を加味する設定になっていないからです。
書店での購入の際も同様ですので注意してください。通常のお支払ではクレジットカードや図書カードを取り扱っている店舗でも、現金のみのお支払となります。
最後に、到着までの期間となります。
これは購入する際に確認することが必要となりますが、書店にある場合には当日購入することができます。
一方で、書店の在庫にない場合には非常に時間がかかることを覚悟した方がよさそうです。
教科書をなくさないような生活習慣
さて、なくした教科書を再び購入できて解決と思いきや!息子さんがまた教科書をなくしたってことはないでしょうか❓
そうしたことがないように願っておりますが、できるものならなくさないような学校生活や日常生活を送ってほしいと思います。
ここではちょっとした意識改革により行うことができる生活習慣をお渡ししましょう👍
●モノを置く場所を決める
●時間をもって行動するようにする
●何かしながら行動しないようにする
●親しい人や家族には会話するようにする
モノをなくしやすい場所と探し方
では、モノをなくしやすい場所と効果的な探し方についてみていきます。
モノをなくしやすい場所(状況)
◆ものが多いところ
こちらはイメージしやすいかと思います。物が多い場所で何かおとしたときにどこにあるかわからなくなりますよね。普段から整理整頓を心がけるようにしましょう。
◆隙間が多い
ふとしたことにより、隙間に書類や本が入ったときに気づきにくいため、モノをなくしやすいです。
◆なんとなくの行動が多い
普段から、物を置く場所を決めてないとものをなくしやすいです。
効果的な探し方
◆動線をたどりながら五感でイメージ
落とした時間帯の動線を何度も往復することが必要となります。その間に何か音がしなかったかと振り返るべきです。
途中で電話がかかってきたときに近くにカバンを投げたけど、「あの時、カバンから落としてないかな?」などです。
そうしたことを1つ1つ振り返っていく作業が必要となります。
◆モノが多いところにアタリをつける
動線を何度か探し回っても見つからない場合は、なくしそうな場所にアタリをつけて探しまわることが必要です。時間をかけすぎると疲れたり、集中力が欠けてきます。
◆書類や本の間を探す
これは、個人的な意見や経験をもとにしたものとなります。
意外に視覚になってしまうのが、教科書やノートであります。教科書を探しているのになんで別の科目の教科書をみるのと思われてしまいますが、本や教科書の間に教科書が挟まっているなんてことは結構あるんですよね笑
モノがぎっしり詰まったランドセルですと、無理やり押し込んだ教科書が別の強化の間にはさまっているなんてこともありえます。
最後に
ちなみに私は教科書を紛失したことはありませんでしたが、部活のロッカーに置いたのに、実は家の中をひたすら探して1週間後に見つかった経験があります(笑)
今振り替えると冷静になって動線をたどっていればよかったのですが!焦って感情的になることが多かったんですよね。
そうしたときには、是非ともこの記事を参考にしてもらえるようにしたいものです👌