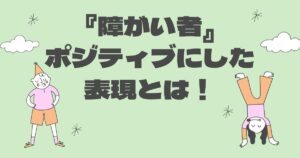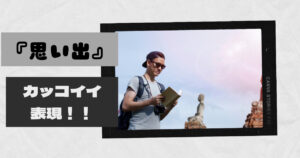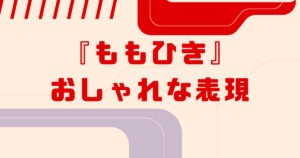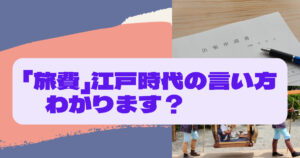『雪解け』よりも古風な言い方を知ることができます!
『雪解け』を目の当たりにすると春の訪れを感じることができるんですが、他にも色んな感情が込み上げてきますね~!
「冬も終わりなんだね~」と思い出を振り返ると懐かしくも切なくも。”冬の終わり=卒業”と本能的に刷り込まれているからかもしれません…..🤔
私自身にとって色んな感情を思い起こさせる『雪解け』は歴史や厚みを感じる言葉であります。
それだけに考えてしまうのがもう少し古風な(歴史を感じさせるような)言い方はないのか⁉
ということで、今回は『雪解けの古風な言い方』についてあれこれ調べて、永久に留めておきたいものをシェアさせて頂きたいと思いますよ~👍
「雪解け」の古風な言い方!
『雪解け』は雪どけ・雪融け、と表記されます。
本題に入っていきましょう。色々調べたなかでも古風な言い方はコレ一択でよいと感じましたのでご紹介させていただきますね😊
『雪解け』も古風な表現と言えるとは思いますが、それよりも古風な言い方はこちら☟
✔ゆきげ
ゆきげ(雪げ)
“ゆきどけ”よりも古風な言い方をすれば『ゆきげ』と表現できます。
漢字に起こすと「ゆきげ」は雪消・雪解とも表記するので、なんとなく「雪解け」と似通っていると思ってもらえるでしょう。
根拠も引用させて頂きますね🙇🏻
ゆきーげ(雪消・雪解):
①雪がきえること。雪どけ
例「この川にもみぢ葉流る奥山のゆきげの水ぞ今まさるらし」出典:古今集②雪解け水。春の季語。「ゆきぎえ」の変化した言葉。
引用元:webilo 古語辞典 ゆきーげ より
うん、「ゆきげ」でありますが古語辞典に掲載されており随分と長い歴史がありますね~🙁
古今集から使われていることば。古今集とは平安時代905年5月24日に作られた歌集。古今和歌集のことですね。全20巻1111首ありますが、「ゆきげ」がでてくるのが第六:冬の320首です。
現在では用いられておりませんが、古今集は現在に至るまで文学や言葉に影響を与えているのは間違いありません。学校で習う国語の教科書にも頻繁に登場!
この河にもみちは流るおく山の雪けの水そ今まさるらし
引用元:国際日本文化研究センター 古今集 より
残念ながら作者は不明となりますが、雪が積もらずに解けて流れている様子を歌ったものですね。雪どけをみて季節を感じるのは時代を問わず変わりませんね。いとあはれなり❕
雪解けに関連した言葉
続きまして、雪解けに関連する表現を雪どけの2つの意味に分けてとみていきましょう。
- “雪がとける“意味
- “わだかまりがとける“意味
①”雪がとける”意味に関連するもの
雪解けに関連する表現は色々ありますよ~。箇条書き形式で並べてみたので確認してみてくださいませ🙇🏻
雪代水(ゆきしろみず)・・・雪解け水
雪汁(ゆきしる)・・・雪どけの水
東風解氷(はるかぜこおりをとく)・・・季語、2/4~2/8頃を表す。東風がふくと寒気がやわらぎ春を感じるといわれます
魚上氷(うおこおりをいずる)・・・季語、2/14~2/18頃を表す。七十二候。少しずつ暖かくなり氷が割れて魚が表れるさま
雪間(ゆきま)・・・積もっていた雪の合間から若草が垣間見える
薄氷(うすらい、うすごおり)・・・仲春の季語、春の初めの季節感をあらわすことば
忘れ雪・・・最後の雪、名残雪(なごりゆき)
雨水(うすい)・・・二十四節気では雪どけが始まる季節感とされます
②”わだかまりが解ける”意味に関連するもの
ご存知かと思いますが、雪が解けるとはもめごとがあった方と和解するという意味があります。
こちらではわだかまりが解けると関連する表現をご紹介していきますね。
わだかまりが消える・・・仲直り
歩み寄る・・・妥協点を譲歩する
和解する・・・確執を解消して関係を回復する
喧嘩を辞める・・・いがみ合いをやめる
最後に
『雪どけ』でありますが、古風な言い方でありましても音の響きはそこまで大きく変わることがなかったのではないでしょうか?元々は”ゆきぎえ”。それが形を変えたことば。
もう少し違った言い方も期待していたのですが、古今和歌集からとは!想像以上に長い歴史があり、それだけでお腹一杯になってしまいました。
にしましても、雪に対して切ないニュアンスを表現した言葉が多い印象です。『雪どけ』を”わだかまりが解ける”という意味合いで用いた方もどこかこのように感じてしまいます。